| [Home] [ [ |
|
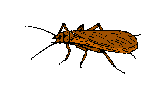 My Little Flyfishing Notebook �l�̏����ȃt���C�t�B�b�V���O�E�m�[�g�u�b�N�@�@My Little Flyfishing Notebook 2.0 �t���C�������ۂ̃|�C���g�Ƃ͉����@Tips for Tying and Inventing flies |
|
| �@ | |
| 2.0 �t���C�������ۂ̃|�C���g�Ƃ͉����@Tips for Tying and Inventing flies | |
�H�|�i�Ƃ��Ẵt���C |
|
| �@���������t���C�t�B�b�V���O�̗��j���炢���A�t���C�^�C�C���O���邢�͗l�X�Ȃƃt���C�p�^�[�����u�`���H�|�i�v�iArt
Craft)�ƂƂ炦�邱�Ƃ͏\���ɉ\�ł���B�H�|�i�Ƃ��Ă̖ѐj�Ƃ����T�O�����܂����s���Ɨ��Ȃ��ނ��ɂ́A�����c����Y���̐��E�I�ɂ������ȃp�^�[���u�b�N����x�J���Ă݂Ăق����B�ނ̎�ɂȂ�t���C�����̔������ɖl�͂��������̂ށB����Ȕ������t���C�������Ă݂����B�����v��Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B��c�u�����h�̖ѐj����x���g�������Ƃ��Ȃ��̂ɂ����̂͋C��������̂����A����͂�͂�u�E�l�v�̎�ɂȂ�u�|�p�i�v�Ƃ����ׂ��N�I���e�B�������Ă���Ǝv����B |
|
 ��c���̃t���C�B�������ɂ����w�Ŕ��������Ă���̂ŁA���\�X���₩���ɍs���܂��B |
|
����Ƃ��Ẵt���C |
|
| �@�������A���̂悤�ȍH�|�i�����ɍ�邱�Ƃ̂ł����p�Ȑl������A�������������̂��݂邩���������炤������ق��Ȃ��ɂ߂ĕs��p�Ȑl������B �@�l�́A���炩�Ɍ�҂��B�����Ƃ��A���{�l���~�j�}���X�g�Ƃ����C���[�W�͊C�O�ł͂����Ԃ鋭���悤���BYorkshire��Bolton Abbey�ɒނ�ɍs�����Ƃ��A�������̃��o�[�L�[�p�[�������}�C�N�Ɂu���{�l�͊�p�ŁACDC�t���C�����ӂȂ낤�H�N�̂��̃{�b�N�X�ɂ���pretty�@little�@Thing����l�ɏ����Ăق����v�Ƃ����܂�Ĕ��ɍ��f�������Ƃ�����B�l�̊������b�c�b�t���C�����{��\�Ƃ��Ȃ��Ă��܂��ẮA�c�コ��Ⓡ�肳��ɂ܂��Ƃɐ\����Ȃ��B�u���{�l�Ƃ������̂͐{����p�ł���v�ƊϔO����̂́A�A�����J�l�����ׂă����L�[�ŁA�C�M���X�l�����ׂĐa�m���Ǝv�����炢�A���I�ȑԓx�ł���B �@ �@����Ȗl�́A�Ƃ��̐̂ɁA�t���C���Y��Ɋ����Ƃ������Ƃ���߂Ă��܂����B�l�ɂƂ��āA�t���C�Ƃ͍H�|�i�ł͂Ȃ��B�t���C�͖l�ɂƂ��Ă͂����܂ŋ���ނ邽�߂́u����v�ɂق��Ȃ�Ȃ��B�������A����ɂ��ւ肪����B���{�l�͋@�\�����d�����āA�������������������邱�Ƃɂ������Ă����B�l�́A�ǂ������̒ނ�����̂Ȃ�A���������@�\����ڎw���Ėѐj�����������Ǝv���Ă���B�������A�@�\�ɂ͉Ȋw�I�ȍ������������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�X�ɂ����A�����������@�\���A�ꏊ��G�߂ɂ��������Ďg�������Ă����A�t���C�t�B�b�V���O�́u�n�����v�Ɓu�헪���v�������ɖ��킦����̂Ȃ̂ł��� |
|
| 2.1.�@�t���C���u���ԁv���u������v���@Do you tie or dress�@your fly? | |
| �@���A�l�́A�̒����ő����������O���m��Ȃ�����a�t���v���o���Ă���B �@ �@2006�N��8���̓��j���A���͂₭����l�ÂĂɕ����������ɓ��k�����l�B�������A���̂���l�̈��p���Ă���ALTMORE�̂W�t�B�[�g5�Ԃ̊Ƃ́A���߂��܂ŋȂ��邱�Ƃ��Ȃ��A�l�̃t���[�K�[���_���X�g���ނȂ������`�F�b�g�����������Ă����B�₪�Ėl��30���[�g���ʐ���a�t���ނ��Ă���̂��������B�u�������A��s�҂̂������v�ƁA�l�͎������Ԃ߂͂��߂Ă������A�ނ͉��ڂł݂�������ł����X�Ƃ��Ȃ��Ă����悤�������B �@ �@�[���O�A�ނ��E�k�ׂ̈ɐ�������Ă����Ƃ��܂ŁA�l�͔ނƂ̋����������Ԃ�L���Ă����B�ނƂ���Ⴄ�Ƃ��ނ̃n���X�̐�ɁA�Ȃɂ��Ԃ����̂�����Ă���̂��������B����ɋC�Â����̂��낤�A�����炭��50�߂����炢�́A�����ŐF���ŁA���炩�Ɍ������ł̒ނ����Ƃ��Ă���Ǝv����������܂�����̔ނ́A�ɂ���Ə��ĊƐ��l�ɓ˂��o���Ȃ���A�u����A�ю��v�ƌ������̂����ł��Y���ꂸ�ɂ���B �@ �@�l�͖ю��ŃC���i��ނ������Ƃ͂Ȃ��B�������A�m���ɖю��ł����͒ނ��B����́A���̂Ƃ��̏�i�����X�v���o���Ɓi�������قǁj�悭�킩��B �@ �@�������A�l�́A�t���C�́u�ю��v�ł͂Ȃ��Ǝv���B�t���C�́u��Ђ��v�ł��Ȃ����A�����́u�P���N�W�����v�ł��Ȃ��B�Ƃ������A���������Ă͂����Ȃ����̂��Ǝv���B �@ �@�l�͖l�Ȃ�Ƀx�X�g��s�����ăt���C���h���X(dress)���Ă���B�t���C�������Ƃ���������u�^�C�C���O�v�ƌĂԂ̂������炭��ʓI���Ǝv�����A�^�C�C���O�Ƃ͕����ʂ�u���ԁv�Ƃ������ƂŁA�C�Ђ������Ԃ̂��^�C�itie)�Ƃ����B�t���C�������̂ƌC�Ђ������Ԃ̂Ƃ�������ނ̓��삾�Ƃ͎v�������Ȃ��B�l�͂�͂�t���C�͒����肽��(dress)�Ǝv���B���ꂪ�l�̂����₩�Ȕ��w�ł���B |
|
| 2..2�@�t���C���u�������v�@Dress your fly roughly�@but�@intentionally | |
�t���C���u�������v�H |
|
| �������A�s��p�Ȗl�͂��������t���C���u���������v���ɏ����Ă����邱�Ƃ��炢�����ł��Ȃ��B �@ �@�l�́A���̒��������t���C�Ƃ����T�O����D���ł���B�������Ƃ́A�������A�Ⴆ�V���c�𒅂�Ƃ��A���̃{�^������ԏ�܂ł�����Ɨ��߂�̂ł͂Ȃ��A�O�Ԗڂ�����܂ł͂����Ȃ���A����ł�����͕��i���ł͂Ȃ��悤�Ɍ�����ƌ������ȃh���X�A�b�v�̂��Ƃł���B �@ �@������A����͂��炵�Ȃ������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B���������l���Ċ����Ƃ������Ƃł���B�������d�v�Ȃ̂��B�@���́u���������l���ăt���C�𒅕����v�Ƃ������z�́A�X���`�����̎��̂悤�Ȕ������瓾�����̂ł���B���p���Ă݂悤�B �@�u�l�Ԃ��A�����A�������A�ς��ƌ��Ċ��Ⴂ�����Ⴄ�悤�Ȋ��o�I�Ȃ��̂��āA�ς��Ȃ��Ǝv���Ă����ł��B�t���C�ł�������܂��\������ɂ́A���̂��镔�����������Ėc��܂������������A���Ă����l�����������ł��E�E�E�E�E���̕ӂ͐���Ȃ��Ȃ����u�X�g���[���T�C�h�v�̏�������ɋ��������ł��B���ł��o���Ă���̂́A��������Ɂu�t���C�͎G�Ɋ�����Ȃ��āA���t�Ɋ�����B������ƒ������Ă܂���v���āA����ꂽ��ł��B������āA���̐l�͖l�ƑS�������l���������Ă�����āA����������ł���v�i�t���C�t�B�b�V���[�A2005�N11�����j�B �@�����Ō����Ă���̂́A�܂�A���I�ȃt���C�ł͂Ȃ��A���ɒ��Ǝv�킹�邤�ȕ������������ăt���C�������Ƃ����l�������B�܂��A�X������́u���Ƃ��A�������O�p�`�ɐ��āA�~��������ɏ�����Ă�������A�������猩���l�́A�V���[�g�P�[�L�����Ďv������Ȃ��ł����v�Ƃ����Ă���̂��A�d�v���Ǝv���B����������A�͕퐫�����p�b�ƌ����Ƃ��̈Î����̕����t���C�ɂ͑���Ƃ������Ƃł���B �@ �@�l�́A���̋L����ǂ�ł���A�n�C�p�[���A���X�e�B�b�N�ȃt���C�ł͂Ȃ��A�����������Î�����t���C�������A�ނ��t���C�̏������Ǝv���悤�ɂȂ��Ă������B �@ �@����́A�X�����̊������J�f�B�X�̃{�b�N�X�̎ʐ^���݂Č���I�ɂȂ����B�܂��A��؎�����̃t���C����D���ł���B���ɂ���яo���Ă������ȃJ�f�B�X��C�t���C�i�̖ѐj�j�����B�l�͂��̓�̎ʐ^����D�����B |
|
�u�������v���u�M�����v�̂���t���C�v |
|
| �@���������t���C�͓����ɋ����u�������v���h���Ă���B����́A���̖ѐj�͒ނ��Ƃ����u�M�����v�ɂȂ���B�@���������A��X�́A���̑O��J�����̑O�Ńt���C���g���̂ł͂Ȃ��B���X�Ə̕ω������̒��ŁA���̈�C���邽�߂Ƀt���C�������B���̃t���C�ɂ͂����ƂłĂ����A�����M������t���C�ɂ́A��ɐ��������Y���B �@ �@�����āA���������t���C���g���Ă���A��͂�����ǂ̂悤�ȏꏊ�ɂǂ̂悤�ȃ^�C�~���O�łǂ̂悤�ɓ������ނ�����肾�B���̂悤�ɖ����V���v���ɂ��Ă����Ȃ���A�ƂĂ��ł͂Ȃ����t���C�t�B�b�V���O�̌���͐������Ȃ��B�v�V�I�ȃt���C�Y���Ă��邱�ƂŒ����ȃA�����J��Mike Mercer�́A�u�I�����Ԉ�����t���C�ł��A���ɃL���X�g���ꂽ��A�����ނ��B�t�ɁA�Ɋ��S�Ƀ}�b�`�����t���C���A�Ԉ���ăL���X�g���ꂽ��A��������\���͂��܂�Ȃ����낤�v�iMike Mercer, Creative Fly Tying, Wild River Press,2005�j�ƌ����Ă���B���̌Â����炠��c�_�ɑ��āA�l�͑S�ʓI�Ƀ}�[�T�[���Ɏ^���������B�������AMercer���A�t���C�Ȃlj��ł��悢�ƌ����Ă���킯�ł͂Ȃ��B����́u�I�����Ԉ�����t���C�v�iA Poorly Chosen fly�j�ł����āA�u�Ԉ���Ċ����ꂽ�t���C�v�iA Poorly Dressed fly�j�ł͂Ȃ��B�����ނɁA�u�t���C�ɂ͐��������d�v�ł���v�Ƃ������炫���Ǝ^�����Ă����ɈႢ�Ȃ��B |
|
| 2.3�@�Ȃ����͂��̃t���C�����킦��̂��HWhy Do they take them? | |
�Ȃ��������͂��̃t���C�����킦��̂� |
|
| �ȏ�̂悤�ɁA�t���C�t�B�b�V���O�͖ѐj���g���ނ�ł���ƒ�`�ł���Ƃ��āA����ɂ��̖ѐj�Ȃ���̂����̒ނ�𐬗�������s���̗v�f�ł���Ƃ��āA���̖ѐj����̉����u�Î��v����̂��A�Ƃ����₢�͂��܂���Ȃ���ɏd�v�ł���B ��ʓI�ȓ����́A�ѐj���Î�������̂́u�a�v�ł���Ƃ������ƂɂȂ�̂�������Ȃ����A���͂����ȒP�ł͂Ȃ��BPeterLapsley��CyrilBennett�́A�Ȃ����͂��̃t���C��������̂��Ƃ����₢�ɎO�̓�����p�ӂ���B �P�@�ނ�͖ѐj���u�H�ו��v�iFood)�ƌ��Ȃ��A�u�v(hungry)����t���C�����킦��B �Q�@�ނ�͖ѐj��H�ו���������Ȃ�(Edible)�Ǝv���A�D��S�iout of curiosity)���炭�킦��B �R�@�ނ�͖ѐj��G���邢�͕��O�҂Ƃ݂Ȃ��A�����̗̕��ƈ��S���m�ۂ��邽�߂Ɂu�U���S�v(out of aggression)���炭�킦��B �iPocket Guide to Matching the Hatch,Merlin Urwin Books,2010,p6�j �@�������A�����̓����͋��������瓾��ꂽ���̂ł͂Ȃ��B�����܂Ől�Ԃ̑z���ł��邪�A�����炭�����炸�Ƃ������炸�Ƃ����Ƃ��낾�낤�B�܂��ALapsley��Bennett�́A�P�����ł͂Ȃ��A�Q�A�R�̗v�f�ɂ��ʔ����iSportingness�j��F�߂Ă���B�t���C�t�B�b�V���O�̖ʔ����́A�ςȖѐj���̂ł��ނ��Ƃ������Ƃɂ��邱�Ƃ͖l���ے�͂��Ȃ����A�����̓����̂����A�����Ƃ��\���\�ō����I�ȕ��@�́A�̖������ɔނ炪�H�ׂĂ���H�ו���͂����ѐj�𓊂��邱�Ƃł��邱�Ƃ͘_��҂��Ȃ��B�����āA���ꂱ�����t���C�t�B�b�V���O�̃G�b�Z���X�ł���A���̒ނ������҂��ɂ�������̂ł���B |
|
��͂�@�\���d�v |
|
| �����Ƃ��A�P�ƂQ�̋��ڂ����ɞB���ł��邱�Ƃɂ͒��ӂ��K�v���낤�B����M�́A�����w�t���C�t�B�b�V���O�}�j���A���v�ɂ����āA�u�����ځv�����u�@�\�v���d�v�ł���Ƃ����d��Ƃ����ׂ��L�q���c���Ă���BJoe�@Humphery�Ɠ�����|�̎w�E�ł���B���Ƀ\�t�g�n�b�N�����A���̂Ƃ���A�J�f�B�X�s���[�p�ƌ����ڂɂ���������ɂȂ�u�Ԃ����邱�Ƃ��w�E���Ă���̂́i�����A�Q�S�|�Q�T���j�A�X�p�[�_�[�p�^�[����D���̖l�Ƃ��Ă͖{���ɔ[���ł���B�܂��A�A�����J�̃����t�J�b�^�[�́ABird'sNest�Ƃ����j���t�p�^�[�����_�C�r���O�J�f�B�X���Î�����t���C�Ƃ��đ��p���Ă���B���̃p�^�[���A�m���ɗǂ������B�l��9���̑�\�I�p�^�[���ł���A���ꂾ���Ő��ʏォ���܂ł�ނ邱�Ƃ��o������ɗD�ꂽ�p�^�[���ł���B �@�J��Ԃ��ɂȂ邪�A�l���g���u�Î����v�Ƃ����T�O�́iLapsley��Bennett�́A�u�͕퐫�vrepresentation�Ƃ������A�Î���suggestiveness�Ƃ��������K�����Ǝv����)�A�l�ԂɂƂ��Ă̂���Ɩ������ɂƂ��Ă̂���Ƃ͈قȂ���̂ł�ƌ������Ƃ�O��Ƃ��Ă���B�n�C�p�[���A���X�e�B�b�N�Ȃ����̖ѐj�́A���X�ɂ��Ă��̖ړI��B�����Ȃ��̂ł����āA�d�v�Ȃ͖̂������̎��_�ɗ������Î����ł���B�l�Ԃ̑��ɂ������u�Î����v�͑��Ȗ����ɏI�����̂Ȃ̂ł���B |
|
| 2.4�@�Î����̌܂̘_�_�@Five Points of Suggestiveness | |
�O��Ƃ��Ắu�`�v�Ɓu�����v |
|
| �����������Î����ɗD�ꂽ�t���C�ɂ́A�������Ƃ̂ł��Ȃ���̑O����悤�Ɏv���B �@��ڂ̂���́u�`�v�iShape)�ł���B�t���C�́A���̌`�ʼn������Î����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�Î����ׂ����̂́A���̖���̍���̑z���͂̕����܂܂ł��邪�A���Ɂu�a�v���u�a�炵�����́v�Ǝv���Ă��炦����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B �@��ڂ́u�K�ȃ}�e���A���̎g�p�v�ɂ��u�����v���B���Ƃ��A�o�����X������A�����Ő▭�ɂ����߂��ׂ����ʂ��J�`�J�`�̐j���łł��Ă�����A����͂����̐����̃S�~�ł����Ȃ��B �@�����Ƃ��A�����������o�����X��}�e���A���̑I���́A�����炭�����݂Ď����ł��������Ă݂āA�̓����邵���Ȃ��̂��낤�B�l�̓X�g�}�b�N�|���v���Θ_�҂����A�ނ�Ȃ����͂悭����T���Ă���B�܂��A��q�̐X���A��ؗ����A�}�C�N�E�}�[�T�[�ADavie�@Mcphaile�̃t���C���D���ł悭�Q�l�ɂ��Ă���B�����̓}�V�ȃt���C��������悤�ɂȂ����̂́A�����������o���̏��Y�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B |
|
�Î����̒T�� |
|
| ����ɂ��킦�āA�Î����Ƃ͈ȉ��̂悤�ȓ_���N���A���邱�ƂŖ����������̂��Ǝv���B �@�@�u�F�v�Ɓu�T�C�Y�v�����̕�H���Ă���^���邢�͍D��ŕ�H���Ă��鐅�������Ƀ}�b�`���Ă��邱�ƁB �@�A�u�L�����L�v���u�������v�����邱�ƁB �@�B�h���C��p���V���[�g�^�C�v�Ȃǂ̐��ʏ゠�邢�͐��ʒ����^�̃t���C�ł���u���C�g�p�^�[���v�����R�ł��邱�ƁA�j���t�ł���u�����v�ɒ��ӂ��邱�ƁB �@���ꂼ����ȒP�ɐ����������B |
|
�u�F�v�Ɓu�T�C�Y�v |
|
| �t���C�t�B�b�V���O�����߂Ĉ�N�����ĂA�t���C�́u�F�v�Ɓu�T�C�Y�v���ɂ߂ďd�v�ł��邱�Ƃɗe�ՂɋC�����B�����̃C���i�͉��ł��H�ׂ�Ƃ������̂����i���}����̖̂l�������̓C���i�̌o��������j�A�쐶�̃��}���A�j�W�}�X�A���邢�͗���ł悭�ނ���ꏊ��C&R��Ԃ̃X���n�߂����́A�F�ƃT�C�Y���ԈႦ�A�Ȃ��Ȃ���H�Ɏ���Ȃ��B���ꂪ�l�̌o�����ł���B �@ �@2010�N6���̓�������ł̂��ƁB������ɏ����J�f�B�X�̃n�b�`���݂��n�߂����܂��A�؋��̎�O�Ŗ��炩�Ƀs���[�p��ǂ��H�����Ă���Ǝv���郉�C�Y�t�H�[��������ɂ݂��n�߂��B�l�͂��̂Ƃ����q�ƈꏏ��Sparkle Floating Caddis��14�Ԃ𐔓������Ă݂����A�����͂Ȃ������B�����ň�C��2X�V���[�g��16�Ԃ̓��t���C�i18�ԑ����j�ɂ����Ƃ���A�������܂ɎO�C�قǒނꂽ�B�F�̓O���[���̃A���_�[�{�f�B�Ƀ��X�e�B�̃A���g�����B������ق��̐F�ɕς���ƑS���_���������B �@ �@���̌o���́A����܂ł̖l�̐F�ƃT�C�Y�Ɋւ���^����m�M�ɕς��Ă��ꂽ�B |
|
�u�L�����L�v�Ɓu�������v |
|
| �ȏ�ׂ̂��F�ƃT�C�Y�������Ƃ��d�v���Ǝv���̂����A�����Ɂu�L�����L�v��u�������v���������邱�Ƃ́A���ꂪ�I�[�o�[�h���b�V���O�ɂȂ��Ă��Ȃ���A���̏ꍇ�������ʂނƌ����̂��l�̎����ł���B �@ �@�l���ASparkle Pupa��Floationg Caddis�ɐ��ȐM����u���Ă���̂͂��̂��߂ł���B���̓�̃t���C�́A�F�ƃT�C�Y��ς��ď�ɏ�����Ă����ׂ��p�^�[�����Ɩl�͎v���B���ꂪ����A�G���N�w�A�J�f�B�X�͂���Ȃ����A�w�J�f�B�X������Ȃ��B�l�͂w�X�p�[�N���Ƃ����I���W�i���i�Ƃ����Ă��N���������t���C���Ɏg���Ă���Ǝv���j���l���āA���p���Ă��邪�AEmergent�@Sparkle�@Pupa���l���o����Gary�@Lafontine�́A�{���ɓV�˂��Ǝv���Ă���B �@ �@�܂��AMike Mercer ��Trigger Nymph�����̍l���Ɋ�Â��Ă�����̂ł���Ƃ�����B���̃p�^�[�����K�{���B���ɃV���[�g�V�����N��16�Ԃ�18�ԂɁA�s�[�R�b�N�̃\���b�N�X�ƃ^�[�L�[�̃Z�R���_���[�N�C���ŃA�u�h���������������̃p�^�[���i�{�f�B�̐F�̓i�`���������x�X�g�B�E�[���̒��A���X�e�B�A�I���[�u�Ŋ�����3��ނ������Ă��邪�A�F�ƃT�C�Y����������ł��\���ɂ�����j�́A���}���Ɏ��ɂ悭�����B�����A���}���ɂ̓r�[�Y�w�b�h�͂Ȃ������ǂ��悤�Ɏv���B�l�͂悭���̃K���ʂ�j�ɏu�Ԑڒ��܂ł������ăw�b�h�ɂ��Ă��܂����A�����20�Z���`�O���N���X�̓��{�̈�ʓI�ȃ��}���ɂ͌��ʓI���B�Ȃ����͂悭�킩��Ȃ�����ǂ��B |
|
�u���C�g�p�^�[���v�Ɓu�����v |
|
| �Ō�ɁA�������N�l���d�����Ă���̂́A�h���C�t���C�����ʂɍ��u���C�g�p�^�[���v�ƃj���t�ɂ�����u�����v�ł���B �@ �@�����̓_���A���炩�Ȓމʂ̈Ⴂ�ނ��̂��Ǝ������Ă���B���Ƃ��ACDC�_���B�R�J�Q���E����H����Ă���Ƃ��A����͐�ΓI�ɒނ��p�^�[���ł��邪�ACDC���G��ĈӐ}�����������i���ʂɂւ���悤�ȕ������j�����Ȃ��Ȃ�ƁACDC�_���͓ˑR�S���ނ�Ȃ��t���C�ɕϖe����B��C�ނꂽ�b�c�b�_�����\���ɕ��������Ȃ��œ��������ʁA�ނ��͂��̋����X�v�[�N�����Ă��܂������Ƃ͈�x���x�ł͂Ȃ��B �@ �@�܂��A�p���V���[�g�^�̂艺����p�^�[���ƃE�B���O�ɃX�`���[�����g�����^�V���t���[�e�B���O�j���t�����ɒމʂ̈Ⴂ�ނ��Ƃ����邪�A��������炩�Ɂu���C�g�p�^�[���v�̈Ⴂ���琶�܂����̂��Ɩl�͎v���Ă���B�l�́A�N�����N�n�}�[�Ɠc��t���[�e�B���O�j���t�A����ɃG���N�w�A�[�̃E�B���O�i�w�ǃR���p���_���̂悤�Ȃ��́j��p���Ă��邪�A��̂��̂����ꂩ�Ō����������̂��B �@���ɁA�j���t�́u�����v�ɂ��Ăł��邪�A����̓\�t�g�n�b�N���ɂ������邱�Ƃ��BMike�@Harding�́A�\�t�g�n�b�N���͔g�ɂ��܂��悤�ɉ��o���邱�Ƃ��L���Ȃ̂��Ƃ����Ă��邪�A�m���ɂ����������������\�t�g�n�b�N���̗v�_�Ȃ̂��낤�B�j���t�̒B�l�ł���Joe�@Humphrey�͂��́u�����v�ɂ������āA�����[�����̂悤�ȃA�h�o�C�X���c���Ă���B �u�����A���������������ʼnH������l�q���݂����Ƃ�����Ȃ�A����͖Y�ꂪ�������i�̂͂����B�H���̂��߂ɔނ�͉��Ƃ����Đ��ʂɏo�悤�Ƃ������̂����A��̒ꂩ�琅�ʂɓ��B���ĉH������܂ŁA�h�ꂽ��A���ł�����A�g�ł�����A�M�����r��������ƁA�������̕�H�X�C�b�`������悤�Ȏ�������������������B�r�j�[����v���X�e�B�b�N�A�F������̐V�f�ނŃ��A���ȃj���t��͕킵�Ă��A�ǂ��������̌��ʂɂ����Ȃ�Ȃ��B�����������������̕�H�Ƃ����������h������̂ł����āA���������̃��A���C�~�e�[�V�����t���C�́A���̓����Ɍ����Ă���̂ł���v�iJoe Humphreys, Trout Tactics,Stackpole,1981�j |
|
| (End 6April 2012) |